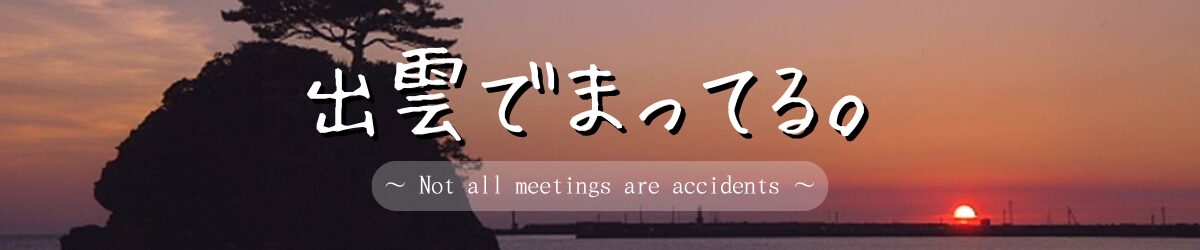本記事はプロモーションが含まれています
出雲大社を訪れる際、「どこから回ればいいのか」「正しい参拝の順番やルートはあるのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、「出雲大社 回り方」と検索して情報を探している方に向けて、参拝方法や境内の歩き方、所要時間の目安まで丁寧に解説します。
縁結びのご利益で有名な出雲大社には、祓社や松の参道、御本殿をはじめとする多くの見どころがあり、それぞれを正しい順番で巡ることで、より深いご縁が結ばれるとされています。さらに、「稲佐の浜の砂」を使った浄化の方法についても触れていきます。
御朱印の授与場所や境内の回り方のポイント、おすすめの食べ歩きスポットなど、初めての方でもわかりやすいように網羅しています。ぜひこの記事を参考にして、出雲大社の魅力を余すことなく味わってください。
・出雲大社の正しい参拝ルートと順番がわかる
・境内の見どころや回るべきスポットがわかる
・御朱印や縁結びのご利益を得る方法がわかる
・所要時間やおすすめの食べ歩き情報がわかる
出雲大社の回り方とは?基本と正しい順番
引用元:出雲大社
- 正門から拝殿までの順番ルート
- 参拝前に立ち寄る祓社の意味
- 松の参道とムスビの御神像の見どころ
- 御本殿と八足門の参拝ポイント
- 出雲大社の正しい参拝方法
正門から拝殿までの順番ルート
出雲大社の正式な参拝ルートは、正門である「勢溜(せいだまり)の大鳥居」から始まります。初めて訪れる方には、この順番で進むことが最も分かりやすく、神聖な流れに沿った参拝ができます。
まず、勢溜の大鳥居をくぐると、全国でも珍しい下り坂の参道が目の前に広がります。参道の右手には祓社があり、後述するようにここで心身を清めてから進むのが基本です。
そこから進むと、小川にかかる「祓橋(はらえのはし)」を渡り、三の鳥居を通過します。その先は「松の参道」と呼ばれる美しい並木道が続きますが、中央部分は神様の通り道とされているため、現在は両脇の舗装された道を歩く必要があります。
松の参道を進むと、右手に「ムスビの御神像」、左手に「御慈愛の御神像」が現れます。これらの神像は、大国主大神の神話に基づく重要なシンボルです。
参道の終点には、四の鳥居である「銅鳥居」があり、この鳥居をくぐると神域「荒垣(あらがき)」に入ります。ここからは一段と神聖な空気が感じられるエリアです。手水舎で清めを行った後、拝殿に到着します。現在の拝殿は1963年に再建されたもので、戦後最大級の木造神社建築とされています。
このように進むことで、自然と神様に近づいていく感覚を得られるのが特徴です。
参拝前に立ち寄る祓社の意味
祓社(はらえのやしろ)は、出雲大社の正門を入ってすぐ右手に位置し、参拝の前に心身を清めるために立ち寄る場所です。多くの神社においても「禊(みそぎ)」の役割は重視されていますが、出雲大社では特にこの祓社の存在が重要視されています。
ここで祀られているのは、「祓戸四神(はらえどのししん)」と呼ばれる四柱の神々です。これらの神々は、人の心や体にたまった穢れを祓う役目を担っています。つまり、神様に対面する前に、自身を清らかな状態に戻すための場だと考えるとよいでしょう。
この祓社を参拝せずに本殿に向かうと、十分に清められないまま神様の前に出ることになってしまうという見方もあります。もちろん、義務ではありませんが、出雲大社の厳かな空気に触れるには、まずこの祓社から始めるのが自然な流れです。
ただし、祓社には小さな賽銭箱があるため、混雑時は人の流れを妨げないよう配慮が必要です。短時間でも心を込めて祈ることで、気持ちがすっと整い、より良い参拝体験につながります。
松の参道とムスビの御神像の見どころ
出雲大社を参拝する際、「松の参道」と「ムスビの御神像」は見逃せないポイントです。このエリアは視覚的にも神聖な雰囲気が漂い、心を落ち着けるのに適した場所です。
松の参道は、出雲大社の境内を流れる「素鵞川(そががわ)」にかかる「祓橋」を渡った先に広がります。ここには樹齢300~400年とされる立派な松が並び、日本の名松100選にも選ばれています。
もともとこの参道の中央は神様の通り道とされ、一般の人は通れないことになっていました。現在も松の根の保護のため中央部は通行禁止となっており、両脇の舗装された道を歩く形になります。
その参道の右手に立っているのが「ムスビの御神像」です。この像は、出雲大社の主祭神である大国主大神が天の神から「幸魂(さきみたま)・奇魂(くしみたま)」を受け取る場面を表現しています。神像の背後には『古事記』からの引用も添えられており、日本神話に興味がある方にとっても学びのあるスポットです。
この参道一帯は、自然と歴史、神話が一体となった神聖な空間です。写真撮影をする方も多いですが、他の参拝者の迷惑にならないよう注意が必要です。
御本殿と八足門の参拝ポイント
出雲大社の核心ともいえる「御本殿」と「八足門」は、参拝ルートの中でも特に重要なスポットです。この場所を正しく理解することで、より深い敬意を持って参拝することができます。
まず、拝殿の奥に位置する八足門(やつあしもん)は、参拝者が御本殿に最も近づける場所として知られています。八足門という名称は、正面に4本、背面に4本の控え柱がある構造から来ており、見た目にも独特な風格があります。
通常はこの門の前で立ち止まり、御本殿へ向けて参拝を行います。ただし、正月の初めなど特別な期間には、八足門が開放され、さらに奥の「楼門」前まで進むことが可能です。このときは、普段見られない御本殿の細部に触れる貴重な機会となります。
御本殿そのものは、1744年に再建されたもので、高さ約24mと国内屈指の規模を誇ります。建築様式は「大社造(たいしゃづくり)」と呼ばれ、日本最古の神社建築様式としても有名です。
注意点として、御本殿のご神体は南ではなく西を向いています。これは、稲佐の浜の方角を向いて鎮座しているためであり、拝殿からの参拝では横から神様にお参りする形になります。神様の正面から参拝したい場合は、御本殿の西側にある「西参拝所」からお参りすることも可能です。
このように、御本殿と八足門の参拝には形式や位置関係への理解が求められます。事前に知っておくことで、より意義深い参拝ができるでしょう。
出雲大社の正しい参拝方法
出雲大社の参拝には、一般的な神社とは異なる作法が存在します。正しい参拝方法を知っておくことで、より丁寧な気持ちで神様と向き合うことができます。
多くの神社では「二礼二拍手一礼」が基本の作法ですが、出雲大社では「二礼四拍手一礼」が正式な手順です。これは、出雲大社の主祭神である大国主大神が、八百万の神々の中心として特別な位置づけにあるためとされています。
作法の流れは次の通りです。
まず、帽子をかぶっている場合は必ず外し、軽くお辞儀をしてから賽銭を入れます。その後、深く2回お辞儀をします。続けて両手を合わせ、右手を少し下にずらした状態で4回拍手を打ちます。このとき、願い事を心の中で唱えるのが一般的です。最後にもう一度、深いお辞儀をして終了です。
この参拝作法は、拝殿だけでなく境内に点在する摂末社でも同様に行います。どの社においても敬意を持った振る舞いが大切です。
出雲大社での参拝は、自身と神様をつなぐ大切な時間です。形式にとらわれすぎる必要はありませんが、心を込めた丁寧な所作が最も重要だと言えるでしょう。
出雲大社の回り方でおすすめルートと楽しみ方

- 境内の回り方で見逃せないスポット
- 縁結びでご利益を得るルート
- 稲佐の浜の砂と素鵞社の清め方
- 御朱印の回り方と授与場所
- おすすめの食べ歩きグルメ
- 出雲大社の参拝にかかる所要時間の目安
境内の回り方で見逃せないスポット
出雲大社の境内は非常に広く、多くの神聖な場所が点在しています。そのため、事前に見どころを把握しておくと、効率よく回ることができます。特に初めて訪れる方にとっては、要所を押さえたルート選びが重要です。
まず注目したいのが、「神馬・神牛像」です。銅の鳥居をくぐってすぐ左手にあり、撫でることで子宝・学業のご利益があるとされています。小さなお子さん連れの方や受験生には人気のスポットです。
次に「十九社(じゅうくしゃ)」です。これは御本殿の東西に一対ずつ並ぶ社で、全国の八百万の神々が出雲に集まる神在月に宿泊する場所とされています。普段は扉が閉じられていますが、神在祭の期間には扉が開き、特別な雰囲気を感じることができます。
その近くにある「釜社」では、宇迦之魂神(うかのみたまのかみ)が祀られており、商売繁盛や五穀豊穣の神として知られています。食に関わる仕事や家庭円満を願う人にはおすすめの参拝スポットです。
また、境内の奥にひっそりと佇む「彰古館」は、出雲大社の歴史や文化を知ることができる建物です。開館日は限られているため事前にチェックが必要ですが、落ち着いて学べる場所として好評です。
時間に余裕がある場合は、「宝物殿(神祜殿)」にも立ち寄ってみてください。古代の出雲大社本殿を支えた巨大な柱の実物が展示されており、その規模と歴史的価値には圧倒されます。
このように、境内には本殿以外にも見逃せない場所が数多く存在します。単に参拝するだけではなく、背景にある神話や歴史に触れることで、より深い満足感を得られるはずです。
縁結びでご利益を得るルート
出雲大社で縁結びのご利益を得たいなら、ルートや参拝順を意識して回ることが大切です。神様に気持ちを届けるためには、単に参拝するだけでなく、意味のある順序で進むことでご縁を結ぶ祈りがより深まります。
まずは、勢溜の大鳥居から正しい参拝ルートに沿って進みましょう。途中の祓社で心身を清め、松の参道を抜けた先の「ムスビの御神像」にはぜひ立ち寄ってください。これは大国主大神が幸魂(さきみたま)・奇魂(くしみたま)を授かる場面を表したもので、縁を結ぶ神の力を象徴しています。
次に、拝殿で「二礼四拍手一礼」の参拝を行い、八足門から御本殿を参拝します。ここでも縁結びの願いをしっかりと伝えましょう。その後は「御慈愛の御神像」や境内に点在する60体以上のウサギの像を巡るのもおすすめです。ウサギは「因幡の白兎」の神話にちなんだ象徴で、それぞれに個性があり、思わぬ縁を感じることがあるかもしれません。
最後に、御守所で縁結びのお守りを授かるのを忘れずに。カード型やストラップ型など種類が豊富なので、自分に合ったものを選びましょう。
縁結びを願う参拝では、急がず心を込めることが大切です。また、ご利益を焦らずに待つ気持ちも大切にしてください。
稲佐の浜の砂と素鵞社の清め方
稲佐の浜で採れる砂と、出雲大社の境内にある素鵞社(そがのやしろ)は、出雲大社の中でも特に神聖なスポットとされています。この砂を使った清めの方法は、古くから「強力な浄化と守りの力がある」として信仰されてきました。
まず、稲佐の浜は出雲大社の西側に位置する海岸で、大国主大神が国譲りの話し合いを行った場所として知られています。この浜にある弁天島の前で手を合わせ、浜辺の砂を少量持ち帰ります。持ち帰る際は、感謝の気持ちを持って静かに行うことが大切です。
次に、境内の最奥にある素鵞社を訪れます。ここには、稲佐の浜の砂を納める「砂箱」が設置されています。参拝後に浜で持ち帰った砂を砂箱に入れ、その代わりに「御砂(おすな)」をいただく流れです。この御砂は、家の敷地や玄関に撒くと厄除けや土地の浄化になるとされています。
さらに、素鵞社の裏手にある八雲山の岩盤に手を当てて、自然のエネルギーを感じる参拝もおすすめです。神様とのご縁をより強める方法として、多くの参拝者が実践しています。
ただし、稲佐の浜で砂を取る行為は常識の範囲で行うこと。大きな袋に詰めるような行動は避け、神聖な場所であることを意識した振る舞いを心がけましょう。
御朱印の回り方と授与場所
出雲大社で御朱印をいただくには、場所と手順を理解しておくことが大切です。御朱印は単なるスタンプではなく、神社とのご縁を結ぶ「証し」として大切に扱われています。
出雲大社の御朱印は、主に3か所で授与されています。最も一般的なのが、拝殿の裏手にある「御朱印受付所」です。ここでは「出雲大社」の印が中央に押された、シンプルで力強い御朱印をいただけます。受付時間は朝6時半から夜7時までと比較的長く、早朝の参拝後にも対応しています。
次に、神楽殿でも別の御朱印を授与しています。御朱印帳を持参している場合は記帳、持っていない場合は書き置きの奉書紙を受け取ることも可能です。初穂料は“お気持ちを”という形ですが、一般的には500円程度を目安にするとよいでしょう。
また、出雲大社の東門を出てすぐにある「北島國造館」でも御朱印が授与されています。こちらでは、御神殿と天神社の2種類があり、受付時間は9時から16時まで。神在月(旧暦10月)には限定の御朱印も登場するため、時期を合わせて訪れるのもおすすめです。
注意点として、混雑する時期は待ち時間が長くなることもあります。時間に余裕を持ち、先に参拝を済ませてから御朱印をいただく流れがスムーズです。御朱印は記念ではなく、心を込めていただく“ご縁の印”として受け取りましょう。
おすすめの食べ歩きグルメ
出雲大社の参拝後は、「神門通り」での食べ歩きも楽しみの一つです。このエリアには、地元の素材を使ったスイーツや郷土料理が揃っており、参拝の余韻を味わいながら一息つくことができます。
まず紹介したいのが、創業240年以上の老舗「出雲そば 荒木屋」です。出雲そば特有の黒みがかった風味豊かなそばを、割子そばや釜揚げそばで味わえます。特に「縁結び天セット」は人気メニューで、見た目も華やかです。
甘いものが欲しくなったら「出雲ぜんざい餅 大社店」がおすすめです。紅白の餅が入った出雲ぜんざいは、神在月に神様へ振る舞われていた神在餅に由来しています。ここでしか味わえない優しい甘さが特徴です。
さらに個性的なのが「大社珈琲」の出雲ぜんざいケーキ。小豆の粒あんとバターのバランスが絶妙で、テイクアウトして神門通りを歩きながら楽しむのにぴったりです。
もう少しゆっくり過ごしたい方には「くつろぎ和かふぇ 甘右衛門」も人気です。抹茶や仁多米を使ったスイーツが豊富で、古民家風の店内で落ち着いた時間を過ごせます。縁結びをテーマにしたメニューも多く、カップルにもおすすめです。
どの店も個性があり、出雲の地元食材にこだわった品揃えです。ただし、昼過ぎには売り切れることもあるため、早めの来店が安心です。食べ歩きも出雲観光の大切な楽しみの一つとして計画に組み込んでみてください。
出雲大社の参拝にかかる所要時間の目安
出雲大社の参拝に必要な時間は、ルートや立ち寄る場所によって大きく変わります。ただし、一般的な目安を知っておくと、旅行のスケジュールを組み立てやすくなります。
基本的な参拝ルート(勢溜の大鳥居 → 拝殿 → 八足門 → 御本殿)だけを巡る場合、所要時間は約60分ほどです。ゆっくり歩き、各所で手を合わせる時間を含めても、この程度で十分回ることができます。
そこに素鵞社や十九社、ムスビの御神像、釜社などを加えると、合計で90分~120分ほどかかります。特に写真を撮ったり、神話に関する説明を読んだりする方は、時間に余裕を持っておいたほうが安心です。
さらに、御朱印の授与やお守りの購入を含めると、もう30分ほど見ておくと良いでしょう。混雑時期には待ち時間が発生するため、トータルで2~3時間を確保しておくと安心です。
また、周辺の観光施設や神門通りの食事処にも立ち寄る場合は、半日から1日かけてじっくり巡るのがおすすめです。短時間でも回ることは可能ですが、出雲大社の持つ神聖な雰囲気をしっかり味わうためには、時間に追われないスケジュールを組むことが大切です。
急ぎ足で回るよりも、一歩一歩を大切にすることが、ご利益を得るうえでも有意義な参拝体験につながります。
出雲大社の回り方を総括
- 勢溜の大鳥居から参拝を始めるのが正式ルート
- 参道に入る前に祓社で穢れを祓っておくとよい
- 松の参道は両脇の道を歩き、中央は避けるのが作法
- ムスビの御神像は縁結びの象徴として必見
- 四の鳥居から先は神域で、より神聖な空気に包まれる
- 手水舎で手と口を清めてから拝殿に向かう
- 西参拝所では神様の正面から参拝ができる
- 正式な参拝作法は「二礼四拍手一礼」となっている
- 素鵞社では稲佐の浜の砂と御砂を交換する風習がある
- 御朱印は御朱印所・神楽殿・北島國造館で授与される
- 食べ歩きでは出雲そばや出雲ぜんざいが人気
- 全体を回るには最低でも2~3時間は確保しておきたい